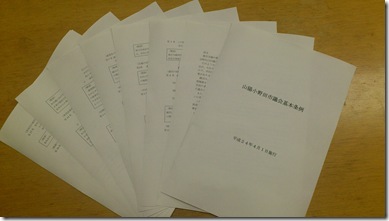議会基本条例制定が及ぼす影響
52回の会議を重ねて平成23年4月1日に議会基本条例が制定されました。
この条例制定により市議会では経験したことのなかった議会報告会や市民懇談会の開催が義務付けられました。
その直後の6月議会の報告会から平成25年6月議会の報告会まで8回、45会場、のべ650名、同様に市民参加型の市民懇談会にはのべ170名の参加がありました。
また、早稲田大学マニフェスト研究所発表の平成24年度議会改革度が1371議会中64位、県内では2位になっていることもあってか、議会基本条例関係で全国他市より12の議会からの視察を受け入れています。
本市議会の動きが先進的な取り組みであるとして議会情報誌である「日経グローカル」や「議会白書」に取り上げられたり「月刊ガバナンス」の取材を受けたこともあります。
でもそんなことは、市民と議会の関係には何の関係もありません。
議会基本条例の目的は、市長と議会との関係、いわゆる2元代表制の政治体制をきっちり確立すること。同時に市民と議会との関係、つまり議会は真の住民代表機関としての位置づけを行動・言論を持って示すことにあります。
全国共通で市民は市長に対しては信頼を寄せ寛大であるにもかかわらず、同じ選挙で選ばれた議会には何故か不信感と狭量心を持って接してきます。
そんな市民感情がやがて批判となって「議員定数削減」を叫ぶか、または無関心層に入り込んでいきます。
昨日の委員会の中でも定数削減の理由として「市民が言っているから」という議員としての限界を感じる意見がありました。
もちろん市民が定数削減を訴えるのは理解ができるところですが、言論を使命とし、議論によって合意を図る議会人はもっと掘り下げて定数論議をする必要があります。
議員の定数は、市長との関係や市民との関係において自治制度の根幹に関わる問題のはずです。そこまで踏み込まない限り選良である議員としての資格がないように感じます。
いくら議員の定数を削減しようとも市民の信頼を得ることができないばかりか、やがて議会不要論まで噴出してくることでしょう。
これまで市民から「議員のくせに議論もできない議員が多すぎる」とか「政治を知らない議員は必要ない」とか「勉強しない議員がなぜいるのか」などと手厳しい意見を聞いてきました。
また、「議会のやっていることが見えない」「何でも賛成する議会は必要ない」「議会はちゃんと仕事をしているのか」という意見も良く聞きます。
つまり、住民は「議員」と「議会」両方に不信感を持っているのです。
やるべき事は議員として議会として活動と言論を通して市民の信頼を勝ち取ることです。
しかし議会基本条例を制定しようともそれは容易なことではないことは分かり切っています。
議会基本条例という改革フレームに肉を付け魂を入れるには、議員の意識変革が必要であると同時に議員力の向上と議会の見える化および議会機能の向上に邁進していく必要があります。
もちろん議員を選ぶのは有権者ですので有権者一人ひとりがしっかりと候補者を見定めることが基本です。
32位です。
クリックすると全国の市町村議員のブログが見られます